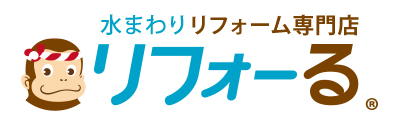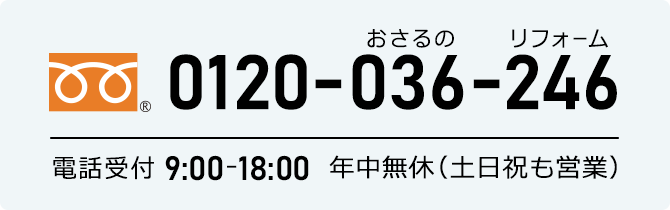ユニットバスは、工場であらかじめ成型されたパーツを現場で組み立てる方式の浴室で、施工が手軽かつ防水性や断熱性にも優れています。本記事では、初心者の方にもわかりやすいように、ユニットバスの定義や歴史、メリット・デメリット、導入時の注意点などを詳しく解説していきます。
これから住まいの新築やリフォームを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
ユニットバスの定義と歴史

まずはユニットバスの基礎知識として、その定義や歴史的背景、システムバスとの違いを押さえておきましょう。
ユニットバスは、壁や床、天井といった浴室を構成するパーツがすべて工場で成型され、現場で組み立てて形成される方式の浴室を指します。従来の在来工法では、現場での防水処理や下地作りが大掛かりとなりますが、ユニットバスはパーツ同士の接合部が防水加工済みで、施工を短期間で進められるのが特徴です。こうした背景から、近年は新築だけでなくリフォームの現場でも広く取り入れられています。
また、ユニットバスは各メーカーが独自の素材や設計を投入しており、防水性や保温性がより強化されたものも数多く登場しています。家庭用だけでなく、集合住宅やホテルのように入れ替わりの多い施設でも、水漏れや劣化リスクを低減できる点が好評です。これにより、幅広い住空間で導入が進んできました。
そもそもユニットバスとは何か
そもそもユニットバスとは、工場成型された床・壁・天井のパーツを現地で組み立て、浴室として完結させるシステムです。現場での防水施工を最小限に抑え、短期間での設置が可能になる点が大きな魅力といえます。また、パーツ全体が防水加工されているため、長期的に見ても水漏れリスクが低い構造になっています。
ユニットバスの歴史
ユニットバスの普及は、当初ホテルやマンションなどの集合住宅で効率的に大量設置できるメリットが注目されたのがきっかけです。工期の短縮や安定した品質が求められる場面において、工場で均一な製品を提供できる形式が重宝されました。その後、防水性やメンテナンス性の高さが評価され、その流れで一般の戸建住宅へも広がり続けています。
システムバスとユニットバスの違い
システムバスもユニットバス同様、規格化されたパーツを組み合わせる方式ですが、メーカーによって呼び方や構造の細部が変わる場合があります。例えば、システムバスは高機能なオプションを追加しやすかったり、素材にこだわった商品展開を行っているケースが多い点が特徴です。一方で、ユニットバスという呼称は、より一般的な規格品全般を指すことが多く、選べる機能や仕様に一定の制限がある場合も見られます。
ユニットバスの種類
ユニットバスには、設置空間や設備構成によっていくつかのバリエーションがあります。
一口にユニットバスといっても、その内部の設備構成や寸法により、複数のタイプが用意されています。特に賃貸住宅やコンパクトな空間を重視する住戸では、バス・トイレ・洗面が一体化したユニットバスが選ばれることも多いです。逆に、戸建住宅や広めのリフォーム案件では、浴床や壁パネルの仕様、設備オプションなどが充実したタイプを好みに合わせて選択できます。
1点ユニットバスとは

1点ユニットバスは浴槽と洗い場だけの非常にシンプルな構成で、最小限の機能を重視する方向けに適しています。限られたスペースに浴室を収めたい場合や水まわりをコンパクトにしたい賃貸物件などでよく用いられます。設備が少ない分、清掃もしやすく、コストを抑えやすいのが特徴です。
2点ユニットバスとは

2点ユニットバスは、浴槽と洗面台が一体となっており、空間を有効活用したい場合に適したスタイルです。少し広めの洗い場に洗面ボウルが設置されるケースもあり、朝の身支度と入浴空間をまとめて確保できます。住宅内のスペースレイアウトに合わせて合理的に設置できることから、リフォーム時にも人気の仕様です。
3点ユニットバスとは

3点ユニットバスは、浴槽・洗面台・トイレが一体化された構造で、限られたスペースを最大限に活用できるのが特徴です。ビジネスホテルや都市型マンションなど、効率的な配置を求められる場面で多く採用されています。一方で、同じ空間にトイレがあるため、使用感や衛生面での好みが分かれることもある点には注意が必要です。
ハーフユニットバスという選択肢

最近では、浴室下半分だけをユニット構造とし、上部は在来工法で自由に仕上げる「ハーフユニットバス」も注目されています。部分的に既製品を活用しながら、壁面などは好みに合わせてタイルや自然素材を使えるため、デザイン性を重視した住宅にも取り入れやすい手法です。防水性や施工期間の面でも折衷案となるため、リフォーム時に柔軟に対応したい場合に検討される方が増えています。
在来工法との違い
現場での防水処理から仕上げまで手作業で行う在来工法と、ユニットバスの差異を理解しておきましょう。
在来工法では、水漏れ対策のためのモルタル塗りやタイル貼りなど、細かな職人技が要求されます。一方、ユニットバスはあらかじめ防水処理が施されたパーツを組み込むため、工期が短く、仕上がりの品質が安定しやすい利点があります。ただし、在来工法でも柔軟なデザインや素材選びが可能などのメリットがあるため、見た目やカスタマイズ性を重視する方は在来工法を検討するケースも多いです。
ユニットバスのメリット
ユニットバスが多くの家庭で選ばれる理由には、主に以下のような利点があります。
ユニットバスは防水性と断熱性に優れており、冬場でも浴室が冷えにくいという特徴を持ちます。また、清掃性が高いため、水垢やカビの発生を最小限に抑えられ、毎日の手入れが楽になる点も注目されています。さらに、施工期間の短縮によってリフォーム費用を抑えやすいことから、初めてのリフォームや限られた予算で検討する方にも取り入れやすい選択肢といえます。
防水性・断熱性が高く、寒さ対策にも◎
ユニットバスは床や壁パネル全体に防水加工がほどこされているため、水漏れリスクが非常に低いのが利点です。加えて、パネル構造と断熱材の組み合わせにより、外気温の影響を受けにくく、冬場でも浴室が冷え切りにくいメリットがあります。これにより、入浴時の温度差によるヒートショックを予防する助けにもなります。
清掃がしやすくメンテナンスが簡単
ユニットバスに使われる素材は汚れが付着しにくく、水切れの良いものが多いため、日常のお手入れが軽減されます。水回り特有のカビや水アカも発生しづらく、掃除が苦手な方でも扱いやすい点が特長です。結果的に、清潔なバスルームを保ちやすくなるのも大きな魅力といえるでしょう。
施工期間が短くリフォーム費用を抑えやすい
ユニットバスは、工場であらかじめパネルを成型・仕上げしているため、現場で行う工程が少なく済みます。解体から設置までにかかる時間が圧縮できるので、賃貸物件など長期間の工事が難しいケースでも導入しやすいです。短期施工は人件費の削減につながるため、結果としてリフォーム費用が抑えられるメリットがあります。
バリアフリーにも対応しやすい
ユニットバスの設計では、床の段差を減らしたり、浴槽のまたぎ高さを低くしたりといったバリアフリー構造を取り入れやすいのが特徴です。車椅子や体の不自由な方でも使いやすく、高齢者や子どもにも安全な浴室が手軽に実現できます。また、手すりを取り付けられるオプションも豊富なため、家族全員が安心して入浴できる環境づくりに役立ちます。
ユニットバスのデメリット
一方、ユニットバスの構造上の理由から、以下のようなデメリットも存在します。
メリットが多いユニットバスですが、規格化されたパーツを用いるがゆえに、自由度の高いカスタマイズには向かない部分があります。また、高い気密性ゆえに湿気がこもりやすいため、日頃の換気などメンテナンスに気を配る必要があります。こうした点を理解したうえで、導入を検討しましょう。
サイズやレイアウトの制限がある
ユニットバスは一定の規格サイズに合わせて生産されているため、住宅の間取りや空間にぴったり合わない場合があります。特に、変形したスペースや梁・柱が複雑に入り組んだ場所には選択肢が限られることもあるため、注意が必要です。希望する配置が難しい場合は、在来工法やハーフユニットバスなど別の選択肢を検討してみるとよいでしょう。
湿気がこもりやすくカビ対策が必要
ユニットバスは気密性が高い一方で、換気が不十分だと湿気が滞留し、カビが発生しやすい点に留意が必要です。特に、日頃から換気扇や窓を積極的に活用しないと、壁や天井にカビがつく可能性があります。定期的な換気や防カビ処理を心掛けて快適に利用しましょう。
規格品であるためデザインやオプションが限られる
ユニットバスは量産品として規格化されているため、オリジナリティのある仕上がりを求める場合には物足りないケースがあります。壁材や色、設備機能などカタログから選択することが多く、細かなデザインの要望が反映しづらいこともあるでしょう。ただし、各メーカーが多彩なデザインラインナップを増やしているので、目的を明確にして選べば十分に満足できることが多いです。
ユニットバスのサイズと選び方
快適な入浴空間を確保するには、ライフスタイルや設置条件に合ったサイズを正しく選ぶことが大切です。
ユニットバスのサイズ表記は「1216」「1317」といった形で内寸を表す数字が使われることが一般的です。これは、表記内の数字が浴室内の幅や奥行きの目安を表しており、実際の設置スペースと照らし合わせて選ぶと失敗が少なくなります。また、マンションと戸建てでは柱や梁の位置、搬入経路などに大きな違いがあるため、購入前にしっかり確認することが重要です。
主な規格サイズの一覧
ユニットバスには、1216(内寸約1200mm×1600mm)、1317(1300mm×1700mm)、1418など、さまざまな規格が存在します。数字が大きいほど内部スペースが広くなり、家族での入浴やゆったり湯船に浸かりたい人には適しています。洗い場の広さも変化するため、シャワー中心の生活か、湯船をしっかり利用するかなどのスタイルを考慮して選びましょう。
一戸建て用とマンション用で異なるサイズ
戸建てとマンションでは、建物構造や搬入経路が異なるため、用意されるサイズや形状にも差があります。マンションの場合、エレベーターや共用廊下を通しての搬入が制限要因となるため、組み立てパーツの分割方法が異なるケースがあります。一方で戸建てはスペースの自由度が高いため、大きめサイズを選びやすいというメリットがあります。
梁・柱・窓のある浴室での注意点
既存の浴室に梁や柱が入り込んでいる場合、ユニットバスをそのまま設置できないケースがあります。工事の段階で一部を切り欠き加工したり、サイズを変更できる商品を選んだりと対処方法はいくつかありますが、そのぶん費用や工期がかさむことを念頭に置きましょう。また、窓がある場合は、採光や換気の面でメリットがある反面、パネルとの取り合い部で施工が複雑になることもあります。
ユニットバス導入・リフォーム時の注意点
実際にユニットバスを導入またはリフォームする際には、以下のような点を考慮しましょう。
ユニットバスを導入するにあたり、まずは現場調査で実際の寸法や配管、搬入経路を確認することが欠かせません。家族構成や利用スタイルといったライフスタイル面も検討し、必要な設備や広さを決めていきます。さらに、施工実績の豊富な業者を選ぶことで、トラブルを回避しスムーズなリフォームを実現しやすくなるでしょう。
搬入経路や設置スペースの確保
ユニットバスは床や壁など大きなパーツを搬入するため、玄関や廊下、エレベーターといった通路の幅や高さに余裕があるか事前に確認する必要があります。賃貸物件や集合住宅では特に制約が多いため、管理組合の許可がいることもあります。工事前にしっかり搬入計画を立てておくことで、当日のトラブルを減らせるでしょう。
家族構成やライフスタイルに合わせる
家族の人数や年齢層によって、浴槽の深さや段差の有無など求める機能が変わってきます。小さなお子さんがいるご家庭では、浅めの浴槽やすべりにくい床が好まれ、高齢者がいる場合はバリアフリー性と断熱性能を重視する傾向があります。入浴の頻度や時間帯も考慮し、生活にフィットする仕様を検討しましょう。
施工実績豊富な業者を選ぶコツ
ユニットバスの導入やリフォームでは、業者の技術力や経験値によって仕上がりやトラブルのリスクが大きく左右されます。実績のある業者は様々なメーカーの製品や施工例を持っているため、最適なアドバイスを得やすいです。価格だけでなく、保証内容や施工後のサポート体制なども含めて比較検討しておくことが成功のポイントです。
ユニットバスの費用と施工期間の目安
購入やリフォームの際には、具体的なコストや施工期間を知っておくとスケジュールを立てやすくなります。
ユニットバスを導入するための費用は、本体価格のほかに解体費用や設置工事費用などが上乗せされます。追加オプションの有無によって総額が大きく変動するため、事前に必要な機能や予算を明確にしておくことが肝心です。また、施工期間は解体や下地処理を含めて数日から1週間程度が一般的な目安ですが、物件の状況や業者の段取り次第で変わってきます。
本体価格とオプション費用
ユニットバス本体はメーカーやグレードによって価格帯が広く、基本的な機能のみのモデルから高級感のある仕様までがあります。換気暖房乾燥機や浴槽の保温機能など、オプションを追加するとその分費用が上がります。ライフスタイルに合わない機能をむやみに付けると予算オーバーにつながるため、優先度をつけて検討しましょう。
解体や設置工事にかかる期間
在来浴室からユニットバスへのリフォームでは、まず既存の浴室設備を解体する段階が必要です。その後、下地の補修や配管工事、ユニットバスの組み立てを行うため、合計で数日から1週間ほどが一般的な目安となります。ただし、梁や柱の位置調整など追加施工が発生した場合、工期が延びる可能性があります。
ユニットバスを選ぶ際のポイント
快適なバスタイムを実現するために、ユーザーのニーズに合った機能とデザインを選びましょう。
ユニットバスを選定する際には、素材や断熱性、清掃性などの実用面だけでなく、デザインやカラーリングも大切な要素となります。毎日利用する空間だからこそ、使い勝手と見た目のバランスをうまくとることが大切です。メーカーごとに多数のバリエーションがあるため、ショールームなどで実物を確認しながら検討すると失敗が少なくなります。
浴槽や壁材の素材・機能をチェック
浴槽素材には人工大理石やFRP、ステンレスなどがあり、それぞれ保温性や耐久性が異なります。壁パネルは汚れが落ちやすい表面加工がされているものが多く、清掃の手軽さに直結します。事前に素材の特徴を知っておくことで、毎日の入浴がより快適になるでしょう。
デザインやカラーリングの選択
ユニットバスは多種多様なカラーリングやパネルデザインが用意されており、インテリアに合わせたコーディネートが可能です。明るい色のパネルを取り入れると空間が広く見え、濃い色を採用すれば落ち着いた雰囲気を演出できます。お好みのテイストをイメージしながら、実際のサンプルで色合いを確認することが大事です。
断熱性や清掃性などの実用面を考慮
ユニットバスを長く快適に使うためには、日々の掃除や光熱費への影響も考慮する必要があります。断熱性が高い浴槽や壁材を選べば、お湯の温度低下を抑えて暖房費を節約できる可能性がありますし、清掃性の高いパネルは時短にもつながります。これらの実用面と快適性のバランスを見極めることが満足度アップのカギとなります。
まとめ
ユニットバスは、防水性・断熱性・清掃性など多くのメリットを備えた浴室形式です。上記のポイントを参考に、快適なバスルーム環境を整えましょう。
従来工法と比べて施工期間が短く、防水性能も高いユニットバスは、新築やリフォームを問わず幅広いニーズに応えられる選択肢です。ただし、サイズやデザインにある程度の制限があるため、導入前にはしっかりと空間の条件や暮らし方を検討しておく必要があります。メリットとデメリットを理解したうえで、自分たちのライフスタイルにあったユニットバスを選べば、毎日の入浴がより快適で楽しいものになるでしょう。
この記事の監修者

リフォームアドバイザー
永井皓介
ガス可とう管工事監督者、石綿建材調査者
お客様へ安心安全な住まい作りをご提案させていただいております。同じ家でもお一人お一人に対して住まいの環境は違います。お困りごとや理想の形をしっかりとお伺いし、プロの目線で最善のご提案が出来るよう取り組んでおります。お客様のご自宅をより良い環境にしていくためのお手伝いを是非お任せいただければと思います。